【ペットと生前整理】飼い主に万が一があったらペットの行末は?
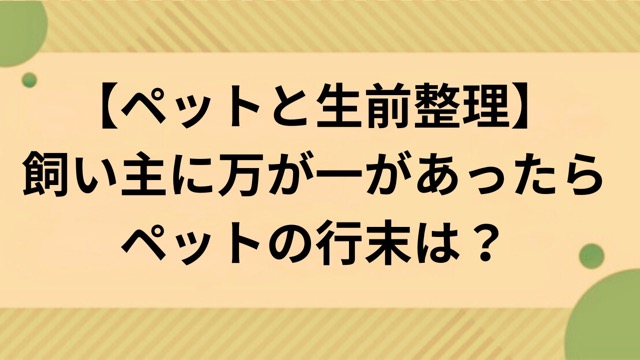
高齢化社会が進む中で「飼い主の万が一に備えて、ペットの今後をどうすればいいのか?」という不安の声が増えています。特に独居高齢者や高齢夫婦で暮らすご家庭では、ペットの命をどう守るかは重要な課題です。この記事では、生前整理の一環として“ペットの将来”について考えるべきポイントをまとめます。
飼い主が急に入院・他界した時、ペットはどうなる?

飼い主が突然倒れたり亡くなったりした場合、ペットの世話をする人が不在になるリスクがあります。特に一人暮らしや同居家族が高齢の場合、近隣との関係も薄く、ペットが数日間放置されてしまうケースも。
多くの市町村では、行政がペットの保護を行う体制は整っていません。動物愛護センターに一時保護される場合もありますが、譲渡先が見つからなければ最悪の事態(殺処分)につながる可能性もあるため、事前の備えが不可欠です。
生前整理の中で「ペットの今後」を話し合っておくべき理由
生前整理というと「物や財産」の整理を想像しがちですが、家族のように暮らしているペットの将来を考えることも、重要な整理のひとつです。
「誰に預けるか」「費用はどうするか」「通院先や食事の内容」など、本人が元気なうちに明文化しておくことで、万が一のときに周囲が混乱せず、ペットの生活も守られます。
ペット信託(ペットのための財産管理)という方法もある
最近では「ペット信託」という制度も注目されています。これは、飼い主が生前に信託契約を結び、ペットの飼育を託す相手と、その費用(信託財産)を管理する人を明確にしておく制度です。
費用例としては以下のような内容が含まれます。
- 餌代やトイレ用品などの生活費
- 動物病院への通院・治療費
- 飼育者への謝礼や見守り費用
信託銀行や専門士業と契約する必要はありますが、確実な管理を希望する方には非常に有効な手段です。
家族や親戚に引き取りをお願いする場合の注意点
ペットを家族に託したいと考えていても、相手の生活環境・年齢・持病・ペットアレルギーなどにより、引き取りが難しいこともあります。
話し合う際には以下の内容を共有しておきましょう:
- ペットの年齢・性格・病歴
- 食事の好みや必要な薬
- 避妊・去勢・ワクチンの状況
- これまでの生活環境(室内/室外、留守番時間など)
言葉で伝えるだけでなく、メモやノート、動画などで記録を残しておくと安心です。
「ペットのための遺言書」やエンディングノートの活用

ペットは法律上「物」として扱われるため、**遺言書に「○○にペットを託す」と明記しても、必ずしも法的拘束力はありません。**しかし、遺言書やエンディングノートに意向を書いておけば、相続人や関係者が意思を尊重しやすくなります。
また、**ペットに関する情報だけをまとめた「ペットノート」を作る人も増えています。食事・投薬・性格・散歩時間など細かなことまで記録し、万が一の時に次の飼い主が迷わずお世話できるようになります。
ペットと暮らす今こそ、備えについて考えてみませんか?
遺品整理や生前整理の現場では、ペットの存在が見落とされがちです。
遺品整理や生前整理のご相談を受けるなかで、「ペットのことまでは考えていなかった」という声も少なくありません。
ですが、ペットも大切な家族の一員。将来のことを少しでも考え始めるきっかけとして、
ペットの生活環境や引き取り先について考えてみることは、大きな安心につながります。
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、いざという時は突然やってきます。
飼い主にとってペットはかけがえのない家族の一員。ご自身の体調や生活環境に変化があったとき、
ペットが安心して暮らせる環境をあらかじめ考えておくことは、大切な備えのひとつです。

以下のような備えの方法が考えられます。
- 引き取りをお願いできる家族・知人がいるか早めに話しておく
- ペットの食事・性格・医療履歴などをまとめた「ペットノート」を作成する
- 必要に応じて、地域の相談窓口や動物保護団体の情報を調べておく
ペットに関するご相談をいただいた際には、可能な範囲で情報提供やご希望に寄り添った対応を心がけております。
「いつか」ではなく「いま」だからこそ、ペットの未来も、家族も守る準備を始めてみませんか。
どこから手をつけたらよいかわからないという方も、お気軽にご相談ください。